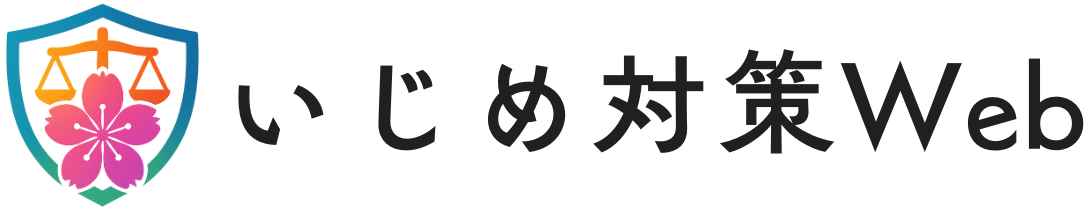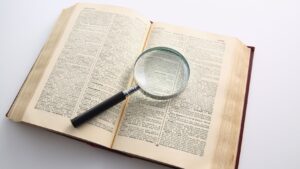いじめの相談先を絞る|ジャムの法則を踏まえた援助要請の促進可能性

いじめを受けた時や見かけたときは、早めに学校へ相談することで事態を解決できることが多いものです。
近年、多くの学校や自治体では、児童生徒が安心して相談できるように、相談窓口を増やしたり、多様な相談手段を整備したりしています。
たとえば、いじめの相談先としてスクールカウンセラーだけでなく、SNS相談、電話相談などが設けられていることが多くあります。「いじめを受けたときは、誰でもいいから相談してね」という言葉もよくある定番フレーズのように聞こえます。
しかし、相談先の選択肢が多ければ多いほど、子どもたちは本当に相談しやすくなるのでしょうか?
むしろ逆に、児童生徒がどこに相談すればいいかわからないと感じてしまう可能性はないでしょうか。
この問いを考えるうえで、「選択のパラドックス」や「ジャムの法則」と呼ばれる心理現象を参考にしつつ考察します。
選択肢が多すぎると人は選べないし不安になる
人は、選択肢が多すぎることで、かえって選択を回避しようとしてしまったり、不幸を感じやすくなってしまうという心理現象があると言われています。
選択のパラドックスとは
選択のパラドックス(the paradox of choice)は、アメリカの心理学者であるバリー・シュワルツ(Barry Schwartz)が、2004年に発表しました。
バリー・シュワルツは著書『The Paladox of Choise』の中で、多すぎる選択肢は不安やストレスに繋がるということを提言しています。
例えば、選択肢がいくつもある中で何かを選択したとき、本当にそれで正しかったのかどうかという不安や後悔がつきものです。
また、選択の際にも、どれか一つを選ぶための時間や労力が必要になります。
よくある認識として「選択肢が多ければ多いほど満足感は高まる」と思い込みがちですが、実は多すぎる選択肢はかえって不満や不幸に繋がってしまい、うつ病に繋がる可能性まであるというこの主張は、多くの人を感嘆させました。
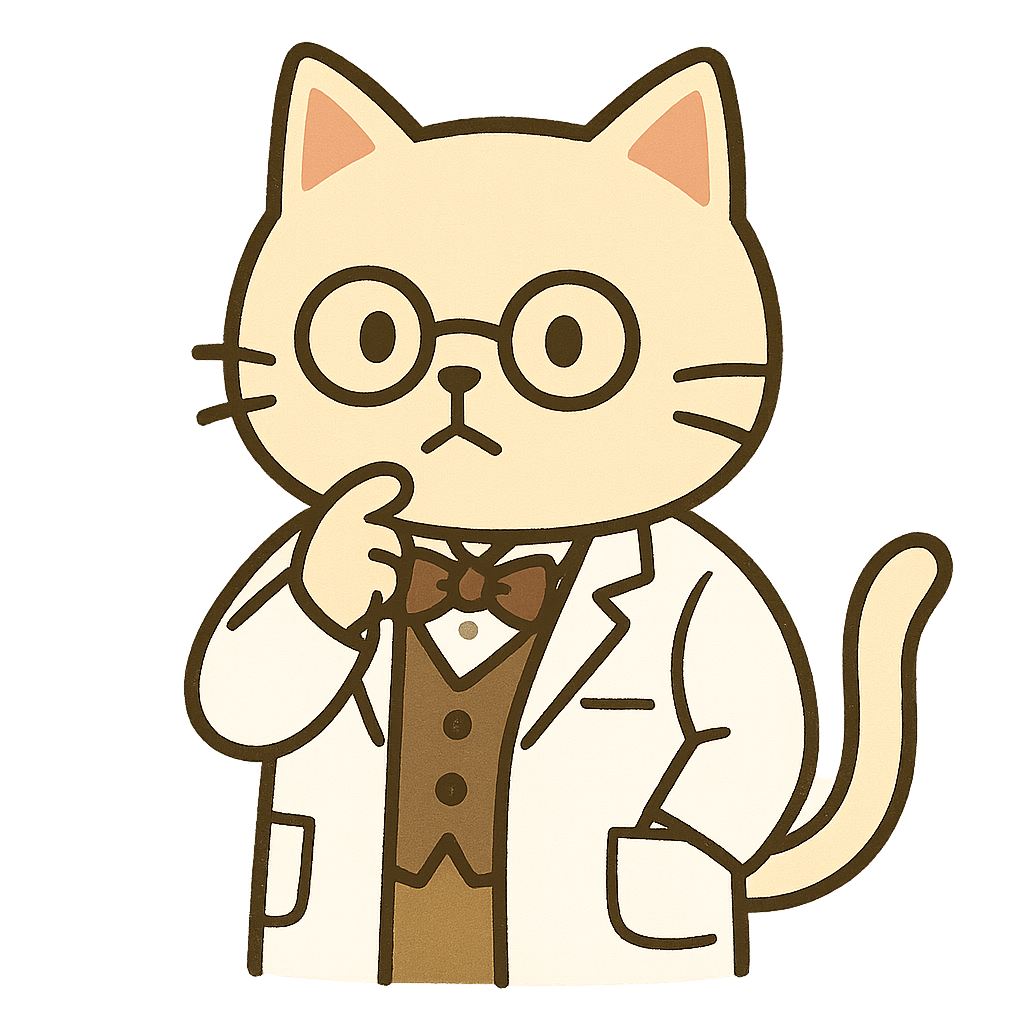
自分で何かを選ぶというのが苦手という声も時々聞きます。つい人任せにしちゃったりというのも、選択のパラドックスに通ずる部分なんですかね。
ジャムの法則とは
ジャムの法則とは、選択肢が多すぎるとかえって意思決定が難しくなるという心理現象です。「選択回避の法則」や、「決定回避の法則」とも呼ばれ、マーケティングや経済学の分野で有名なようです。
この法則は、コロンビア大学のシーナ・アイエンガー氏によるジャムの実験が基になっています。
ジャムの実験(Jam Study)
ジャムの試食販売コーナーを2グループに分け、24種類のジャムを置いているコーナーと6種類のジャムを置いているコーナーとで購買数などを比べた実験です。最終的にジャムを買った割合として、24種類のコーナーは3%、6種類のコーナーの人は30%、という10倍の差があったという結果が出たそうです。
ジャムの実験の説明がされているyoutube動画は以下になります。
この実験から、選択肢が多いと人は選ぶことが億劫になり、行動が抑制されてしまうということが示唆されます。
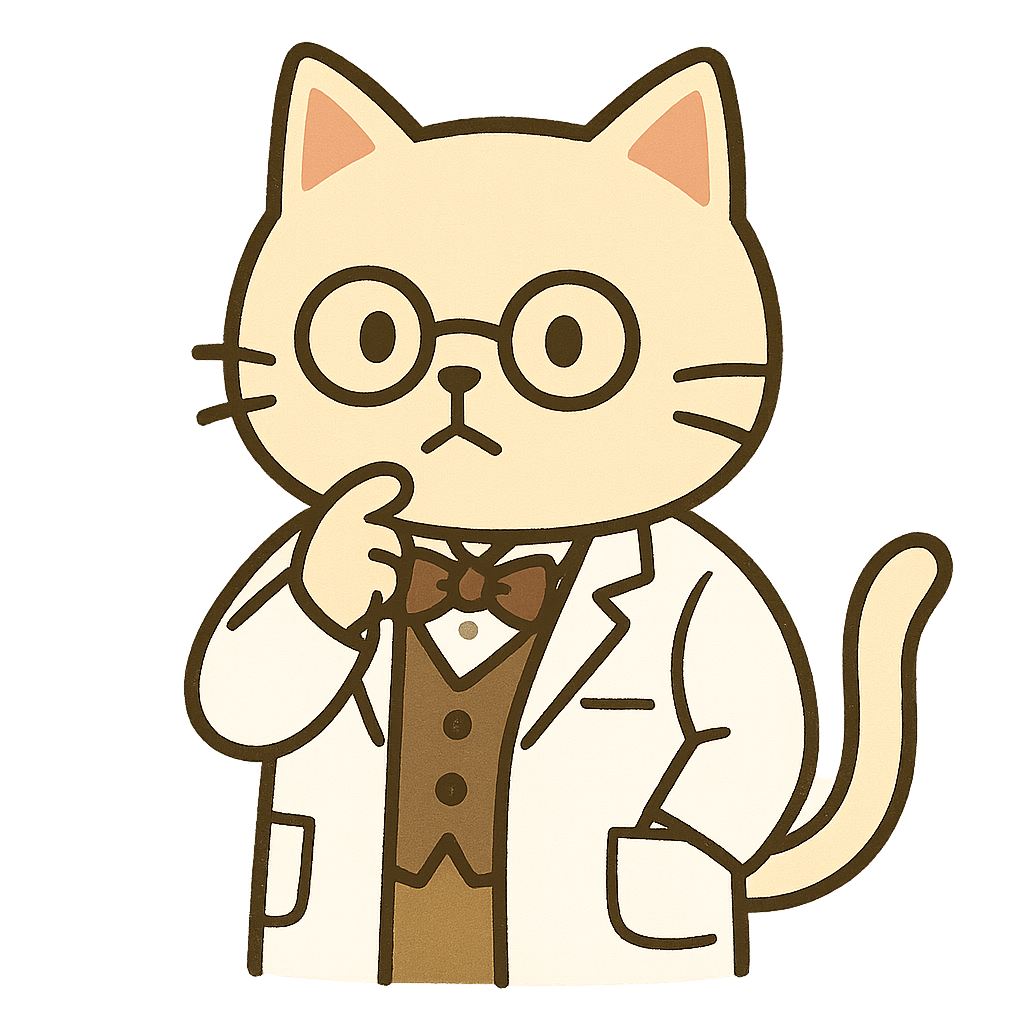
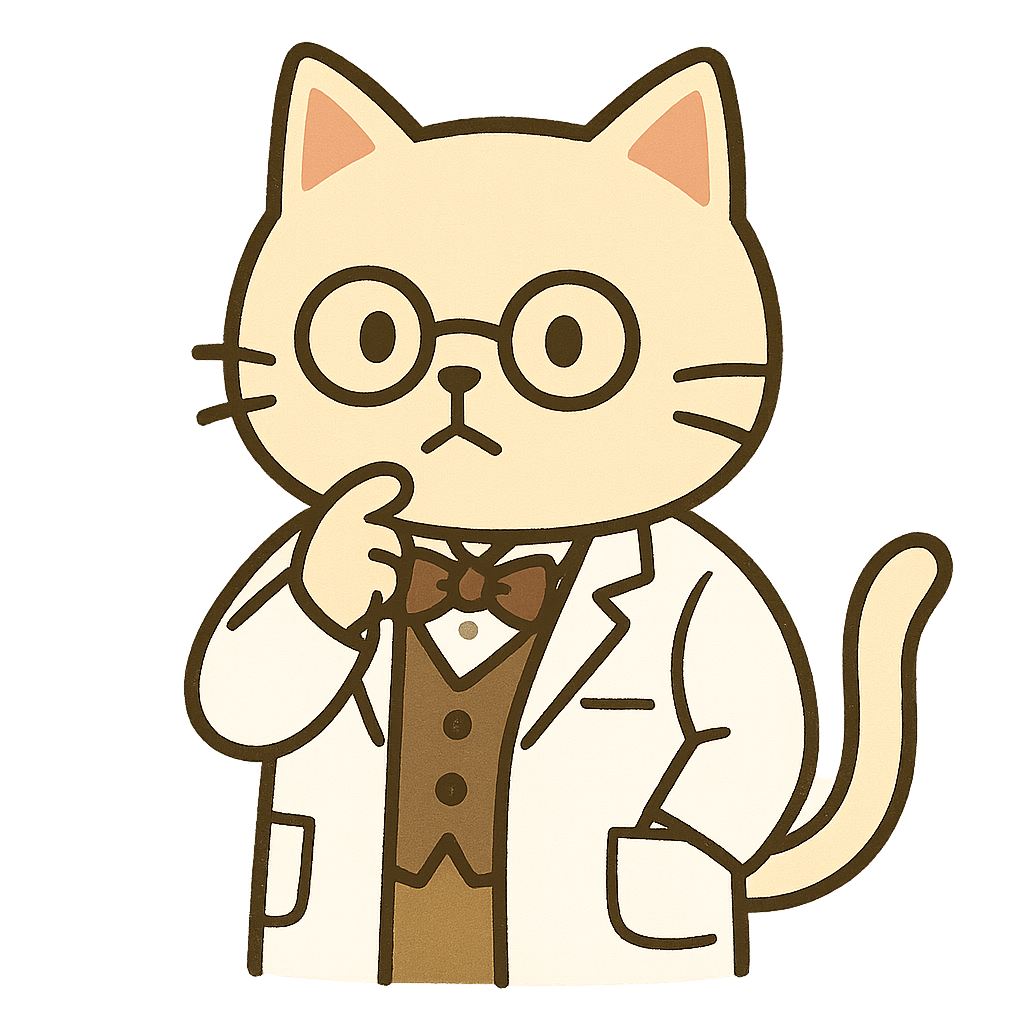
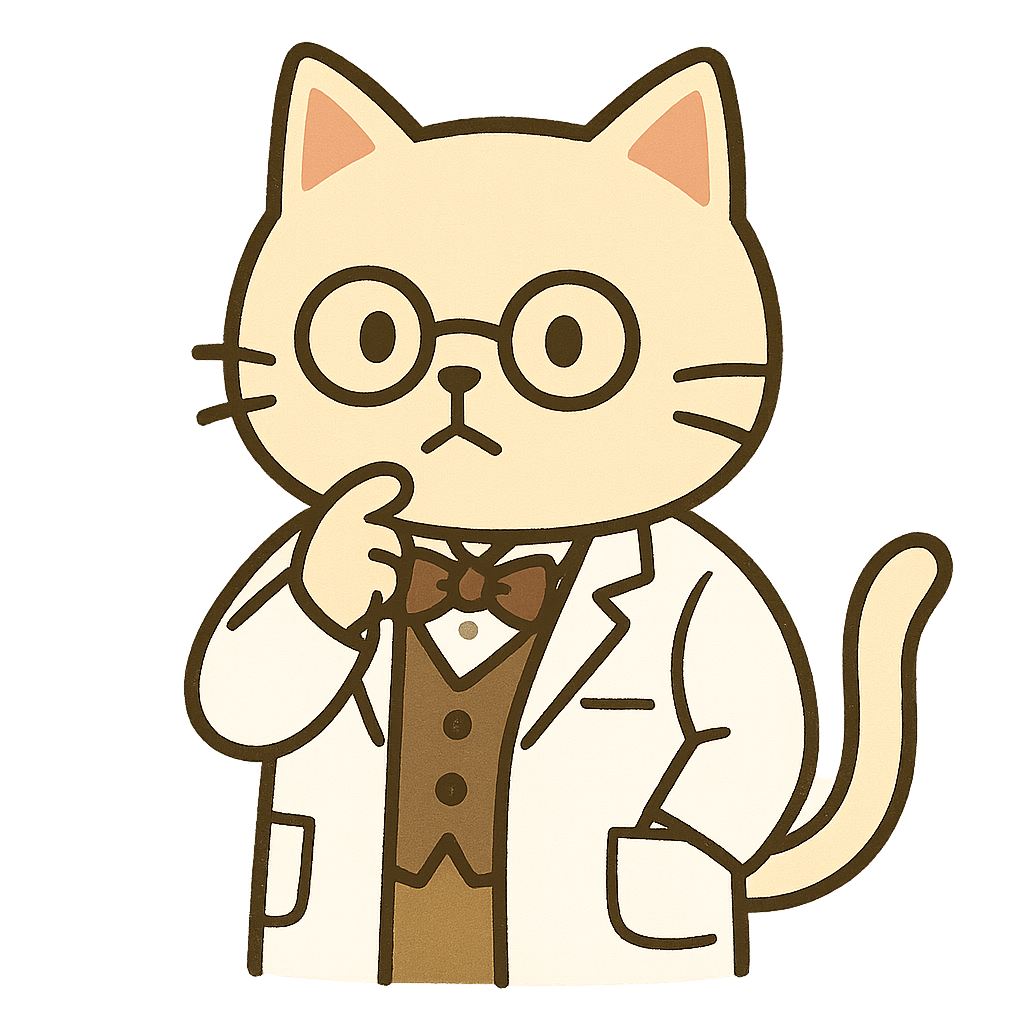
たとえば飲食店でメニューが多いと嬉しいような気もするけど、定番の日替わり定食みたいなのがあると、選ぶ手間が省けて有難いですよね。
いじめの相談先は複数提示されることが多い
インターネットにていじめの相談先を検索してみると、選択肢を複数提示されることが非常に多いです。
例えばGoogle検索で「いじめの相談先」と検索してみたところ、一番上に出てきたのが政府広報オンラインのページでした。このページでは、「みんなの人権110番」、「こどもの人権110番」、「こどもの人権SOSe-メール」、「LINEじんけん相談」、「こどもの人権SOSミニレター」、「24時間子供SOSダイヤル」など、多くの相談先が掲載されており、「いろいろな相談先があります」という文言が強調されているようにも見受けられます。
他にも、検索で上位に出てきた、県や文部科学省によるホームページでも、「相談窓口一覧」と題して、様々ないじめの相談先の選択肢が表に掲載されています。
いじめの相談先が多いメリットを考える
いじめの相談先が多く提示されているメリットとしては、「助けになってくれる存在がたくさんある」というイメージの伝達が考えられます。
他にも、もし一つに相談して繋がらなかった場合や、望むような対応が得られなかった場合に、他の選択肢がセーフティネットになることが挙げられます。
いじめの相談先が多いデメリットを考える
いじめの相談先が多いと、まず相談者はどこに相談すべきか迷わなくてはなりません。
前述した選択のパラドックスの項目で述べたように、人は多すぎる選択肢に対して不安やストレスを感じることがあります。
選択をするということが、労力になるわけです。
いじめで苦しんでいて、相談をしようかと考えている状態の時は、心身が疲れ果てて非常に弱っている状態であることが想像されます。
そんな状態では、相談先の選択というちょっとした労力も、大きな負担になりかねません。
そのため、ジャムの実験のように相談者の行動が抑制されて、結局相談しないことを選んでしまうリスクが考えられます。
また、もし望むような回答を得られなかった場合、自分が選んだ選択肢で望む結果が得られなかったという体験は、失望や無力感を増大させるリスクも考えられます。
援助要請行動を促進するために
いじめの被害者が、誰かに相談するという援助要請行動をとりやすくなることは重要です。
そのために、選択のパラドックスやジャムの法則から、以下のような案が考えられます。
いじめの相談先を絞るという考え方
いじめの相談先を多く提示することにデメリットがあるという考えのもと、生徒に提示するいじめの相談先を絞るという考え方も大事だと思います。
たくさんの選択肢を提示しても、子どもはそもそも大人に比べて選択するということが苦手です。
判断力が未熟だったり、特に先生の言うことをよく聞くようないわゆる優等生の子であるほど、自分で何かを選択するという経験が乏しいということも考えられます。
そのため、いじめの相談先がたくさんあることは、かえって援助要請行動の抑制に繋がりかねません。
教師が外部の相談先を提示する危険性
学校で担任の先生が、いじめ相談先の電話番号が書かれたカードを配るというのは、よくある光景です。
しかし、それがかえって、「いじめの相談は先生以外にしなさい」という無言のメッセージと捉えられてしまい、信頼感を損なうことに繋がる危険性は考えられないでしょうか。
実際に、いじめ相談先のカードに対して言及している中学生の声も見受けられます。
いじめ相談先のカードを配ることが必ずしも良くないというわけではありませんが、児童生徒の受け取り方は多種多様です。信頼性低下のリスクは看過できません。
配る際に、「こういう選択肢もあるけど、いじめで悩んだら先生に気軽に相談してな」という声かけをするなどの工夫は必要ではないでしょうか。
いじめ相談先のカード以外にも、担任教師がスクールカウンセラーを紹介する際にも、こういった注意は必要だと思います。担任教師の態度や信頼性は、いじめ防止のための集団規範を高める上でも非常に重要なファクターです。


信頼できるいじめ相談先の明確化が必要である
援助要請行動を促進するために最も重要なのは、信頼できるいじめの相談先を一つ、明確に示すべきだと私は考えています。
例えば以下の記事であれば、私は学校のいじめ対策組織に相談することをおすすめとして挙げています。


根拠として、いじめの防止等のための国の基本方針では、学校いじめ対策組織が相談を受け付ける窓口となることが求められています。


とはいえ学校のいじめ対策組織に相談すると言っても、具体的にどの先生に相談すべきかが分からないので、理想としては各学校にいじめ相談を受け付ける担当の教師を確立しておくことが重要だと考えます。
そのためにも、各校の学校いじめ対策組織には、組織をまとめたり相談窓口となるいじめ対策担当教員を導入することが必要不可欠であると私は考えています。


いじめの相談先をできるだけ具体的かつ明確にしておくことで、児童生徒は相談先に迷うことが無くなります。その結果、援助要請行動が促進されるのではと考えています。
このことは選択のパラドックス、ジャムの法則が論拠になるかと思います。
実例としましても、フィンランド発のいじめ対策プログラムである「KiVaプログラム」では、休み時間に当番の教員が目立つベストを着用して見回り活動をすることになっています。
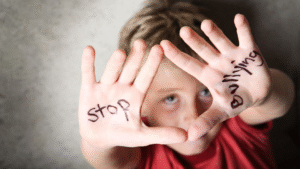
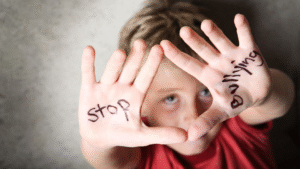
そういった相談先の明確化という取り組みが、児童生徒がいじめを相談する際の障壁や不安を取り去ることに繋がるのではないでしょうか。
信頼できる相談先の明確化が実際に援助要請行動を促進するのかどうか、エビデンスを取ることはなかなか困難に思われますが、今後そういった研究が進むことも期待したいと思います。