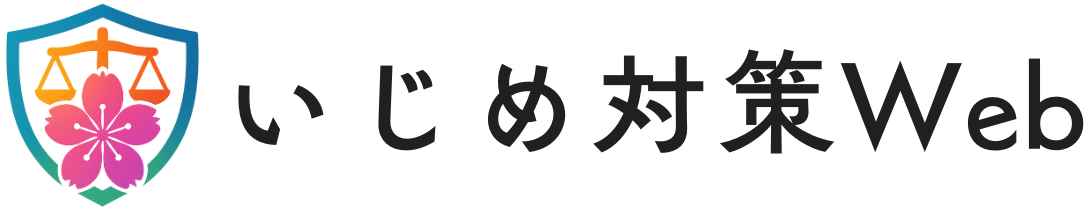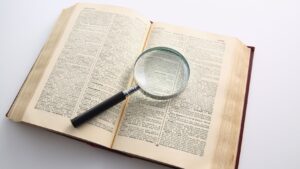いじめの重大事態とは|重大事態1号・2号の違いと定義

いじめの重大事態とは、いじめによって被害児童生徒の学校生活や心身に極めて大きな影響を及ぼす事態を指します。
これは、いじめ防止対策推進法によって明確に定義されており、重大事態と判断された場合、学校や教育委員会は迅速かつ厳正な対応を行うことが義務づけられています。
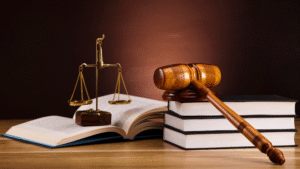
この法律では、重大事態を大きく分けて2つのケースとして規定しており、それぞれ「1号重大事態(1号事案)」と「2号重大事態(2号事案)」と呼ばれることが多いです。
本記事ではいじめ重大事態の定義について、1号事案と2号事案の違いも明らかにしつつ解説します。
いじめ重大事態の定義(いじめ防止対策推進法 第28条第1項)
いじめ防止対策推進法第28条第1項では、以下のいずれかに該当する事態を「重大事態」と定義しています。
| 区分 | 通称 | 定義 |
| 第1号 | 生命心身財産重大事態 | いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 |
| 第2号 | 不登校重大事態 | いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 |
1号重大事態(生命心身財産重大事態)
1号重大事態は、その定義から読み取れるように、被害が深刻なものであるという「質」の側面を重視しています。
そのため、被害の重大さが判断の基準となり、いじめが行われた回数や生徒の欠席日数などには関わらず、いじめの被害が重大であれば1号重大事態に該当します。
2号重大事態(不登校重大事態)
2号重大事態は、いじめが原因で長期間の欠席を強いられているという疑いがあると認めるときに該当します。
期間の目安としては、年間30日の欠席とされています。
ただしガイドラインでは、児童生徒が一定期間連続して欠席しており、その要因としていじめが考えられるような場合には、欠席期間が30日に到達する前から学校は設置者に報告・相談し、情報共有を図るとともに、重大事態に該当するか否かの判断を学校が行う場合はよく設置者と協議するなど、丁寧に対応することが必要だと述べられています。
つまり、30日間の欠席を待たずとも、いじめが原因で欠席が続いていると疑われる場合は、学校が重大事態として迅速に対応を開始することが肝心です。

30日間はあくまで目安です。いじめが原因と疑われる欠席があれば、すぐに重大事態として然るべき対応を開始しましょう。
重大事態と認定される具体例
- 児童生徒が自殺を企図した場合。
- 暴行により骨折や脳震盪などの重大な傷害を負った場合。
- いじめが原因で心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神疾患と診断された場合。
- 高額な金銭を脅し取られるなど、財産に大きな被害が生じた場合。
他にも、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」では以下のような例が挙げられています。
- リストカットなどの自傷行為を行った。
- 暴行を受け、骨折した。
- 投げ飛ばされ脳震盪となった。
- 殴られて歯が折れた。
- カッターで刺されそうになったが、咄嗟にバッグを盾にしたため刺されなかった。
- 嘔吐や腹痛などの心因性の身体反応が続く。
- 多くの生徒の前でズボンと下着を脱がされ裸にされた。
- わいせつな画像や顔写真を加工した画像をインターネット上で拡散された。
- 複数の生徒から金銭を強要され、総額1万円を渡した。
- スマートフォンを水に浸けられ壊された。
なお、これらはあくまで例示であり、ここに掲載されていないものやこれらを下回る程度の被害であるもの、診断書や警察への被害届の提出がない場合であっても、総合的に判断し重大事態と捉える場合があります。
なお、いじめにより転学等を余儀なくされた場合も当然重大事態として扱います。具体的には、重大事態の目安である30日には達していないものの、欠席が続き当該学校へは復帰ができないと判断し、転学(退学等も含む)した場合です。
重大事態の定義を理解し、迅速な初期対応を
いじめ重大事態の定義が法で明確にされているのは、深刻な事態への初期対応を確実にするためです。
学校や教育委員会が「重大事態」と認識することで、迅速かつ組織的な対応が開始され、被害生徒の心身の健康を守ることにも繋がります。
重大事態の定義および1号重大事態と2号重大事態の違いを理解することは、いじめの深刻な被害を様々な角度から捉え、どのケースも見落とすことなく、被害児童生徒の安全と権利を守るための第一歩となることでしょう。
なお、重大事態発生前の日ごろから、学校いじめ対策組織を中心とした組織的対応が為されるべきであることは言うまでもありません。


いじめは未然予防が重要であり、重大事態が発生する前に組織的な取り組みによって、いじめを防止することが重要です。