いじめ防止対策推進法とは|いじめの定義や学校の義務を簡単に解説

いじめ防止対策推進法は、2013年(平成25年)に制定された日本の法律です。
主にいじめ防止のための対策の基本となる事項を定めたものであり、いじめを社会全体で解決すべき課題として捉え、学校、教育委員会、地域、国が連携して対応するための枠組みを定めたものと言えるでしょう。
今回はいじめ防止対策推進法に記載されている、いじめの定義や学校の義務について、できるだけ簡単に解説したいと思います。
いじめに関する法律について学びたい教職関係者の方は勿論のこと、現在いじめに対峙している児童生徒や保護者の方も本法について詳しく知る機会となれば幸いです。

いじめ防止対策推進法は、いじめから子どもを守るための法律です。大人も子どももしっかりと理解していきましょう。
いじめ防止対策推進法の「いじめの定義」
いじめの定義は、いじめ防止対策推進法の第二条に記載されています。
(第二条)
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
やられた方が苦痛に感じればいじめである
いじめ防止対策推進法におけるいじめの定義を簡単に言えば、「やられた方が苦痛に感じればいじめである」ということです。
たとえいじめた側が「遊びだった」「悪気はなかった」と主張しても、いじめられた側が苦痛を感じていれば、それはいじめとして扱われます。
いじめの定義はこれまで何度も変わってきていますが、今回のいじめの定義はかなり幅広いものとなっており、被害者側に寄り添っていじめの認定がしやすくなった一方で、広すぎるいじめの定義に「おかしい」「言ったもん勝ち」と感じるとの意見もあり、賛否両論となっています。
第三者の判断が考慮されていないことは問題であるとの観点から、客観的いじめ判定基準の策定を試みる取り組みもあります。
例:小学校における「いじめ認知」に対する客観的評価基準の検討 : 「いじめ深刻指数」導入の試み
加害者側がいじめを認めないことも多い
いじめを、加害者側が認めないケースは多くあると見受けられます。加害児童や保護者の言い訳として、「やっていない」「そんなつもりじゃなかった」「遊びだった」というのは常套句です。
そのような場合にうやむやになることを防ぐため、今回のように「被害者側がいじめだと感じればいじめである」という定義にしたのだと伺われます。
確かに、いじめの証拠を掴むのは難しいことです。いじめ防止対策推進法におけるいじめの定義は、いじめを受けた側をしっかりと守り通すという意思に則ったものであると考え、個人的には肯定的に捉えています。
ただし、冤罪が起きるようなことは絶対にあってはならないことです。いじめの判断については、教員一人が勝手に行うのではなく、学校全体で組織的かつ慎重に行う必要があるでしょう。
「いじめの禁止」と加害生徒への懲戒
いじめ防止対策推進法の第四条には、いじめの禁止が記載されています。
(第四条)
児童等は、いじめを行ってはならない。
いじめをしてはいけないということが改めて法律で明文化されたわけですね。
いじめた児童生徒への懲戒
文部科学省による「いじめの防止等のための基本的な方針」において、「いじめた児童生徒への指導又はその保護者への助言」についての記載がされています。
その中で、「教育上必要があると認めるときは,学校教育法第11条の規定に基づき,適切に,児童生徒に対して懲戒を加えることも考えられる。」との記載も認められます。
ただし、懲戒は教育的配慮に十分に留意し、いじめた児童生徒が自ら行為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す目的で行うこととされています。
いじめの加害者に対してどのように対応するかということも、また教育現場が抱える課題であると感じられます。


いじめに対する学校の義務
いじめ防止対策推進法においては、学校のいじめへの対処方法が述べられています。学校が講ずべき施策と、対応の中心となる組織について見ていきましょう。
学校いじめ防止基本方針の策定
いじめ防止対策推進法の第十三条により、各学校は「学校いじめ防止基本方針」を策定することが定められています。
(第十三条)
学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。
また、国の基本方針によれば、各学校は、学校いじめ防止基本方針に基づいて、学校の実情に応じた対策を推進することが求められています。
学校いじめ防止基本方針は、基本的に各学校のホームページにて公表されています。
学校が講ずべき基本的施策
主に「第三章 基本的施策」(第十五条~第二十一条)の部分で、例えば以下のような学校が講ずべき施策が挙げられています。
- 道徳教育及び体験活動等の充実
- 早期発見のための措置
- 相談体制の整備
- 関係機関等との連携の強化
- 広報や啓発活動の実施
また、続く「第四章 いじめの防止等に関する措置」(第二十二条~第二十七条)では、特に重要な点である学校の組織的対応についての記載が示されています。
いじめの防止等の対策のための組織
いじめ防止対策推進法の第二十二条には、いじめの防止等の対策のための組織についての記載がされています。
(第二十二条)
学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。
この条文において、各学校には「いじめの防止等の対策のための組織」を置くことが義務付けられたわけです。通称、学校いじめ対策組織や22条組織と呼ばれたりもします。
この組織は、参議院議員である小西洋之氏の著書によれば、「本法におけるいじめ防止等の対策の中核的な仕組みとなるものです。」と解説がされています。(「いじめ防止対策推進法の解説と具体策」より)
これまでのいじめ事案では、担任教師の“かかえこみ”といった問題も見受けられました。
そのため、特定の教職員で問題を抱え込まず学校が組織的に対応することにより、複数人による状況の見立てが可能となることや、必要に応じてスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー、外部専門家等が参加しながら対応することで、より実効的にいじめの解決が期待されています。


学校いじめ対策組織の役割
いじめ防止対策推進法の第二十二条に基づく「学校いじめ対策組織」の役割としては、以下のようなものが挙げられています。
【未然防止】
✧ いじめの未然防止のため,いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割
【早期発見・事案対処】
✧ いじめの早期発見のため,いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割
✧ いじめの早期発見・事案対処のため,いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録,共有を行う役割
✧ いじめに係る情報(いじめが疑われる情報や児童生徒間の人間関係に関する悩みを含む。)があった時には緊急会議を開催するなど,情報の迅速な共有,及び関係児童生徒に対するアンケート調査,聴き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う役割
✧ いじめの被害児童生徒に対する支援・加害児童生徒に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する役割
【学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組】
✧ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う役割
✧ 学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき,いじめの防止等に係る校内研修を企画し,計画的に実施する役割
✧ 学校いじめ防止基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い,学校いじめ防止基本方針の見直しを行う役割(PDCA サイクルの実行を含む。)
これらは「いじめの防止等のための基本的な方針」のp.26-27よりそのまま引用したものです。
いじめ防止対策推進法の第二十二条では組織の設置についてしか記載されていませんが、学校いじめ対策組織の役割は多岐にわたります。教員はしっかりといじめの防止等のための基本的な方針(国の基本方針)や、生徒指導提要を読み込んでおくことが重要です。


生徒指導提要において、「いじめへの対応において、組織が効果的に機能していないために重大事態が引き起こされるケースが見られることから、学校内外の連携に基づくより実効的な組織体制を構築することが課題となっています。」との記載もあるように、組織が十分に機能していないことによる弊害も多く指摘されています。組織的対応の徹底は、今後のいじめ対策における重要な課題です。
「重大事態」と学校による対処
いじめ防止対策推進法の第二十八条において、いじめの「重大事態」は以下のように定められています。
(第二十八条より一部抜粋)
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
それぞれ、1号重大事態、2号重大事態という呼び方をされることもあります。
一例ですが、いじめの被害を受けた生徒が自殺に追い込まれたり、大怪我を負わされた場合は1号重大実態となります。いじめによって生徒が不登校へと追い込まれた場合は、2号重大事態となります。


学校の設置者又はその設置する学校による対処
学校の設置者又はその設置する学校は、重大事態への対処として、速やかに組織を設け、質問票の使用などにより事実関係を明確にするための調査を行うものとされています。
また、学校の設置者又はその設置する学校は、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して必要な情報を適切に提供するものとし、情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとされています。
いじめの定義は幅広いですが、重大事態に認定されたいじめは、特に被害を受けた生徒の生命や人権を脅かすものです。学校は重大事態が認められた場合は、全力で関係機関と連携しつつ対処しなければなりません。
また。日ごろからいじめ及び重大事態の未然防止に努めることが肝心なのは言うまでもありません。
いじめ防止対策推進法はいじめから子どもを守るための法律である
いじめ防止対策推進法が制定された背景としては、2011年に大津市で発生した男子生徒のいじめ自殺事件がきっかけとなっています。
児童生徒同士で行われているいじめに対し、学校が見て見ぬふりをするようなことは決して許されることではありません。本法は、いじめに対する学校や行政等の責務をはっきりと規定しています。
学校は、いじめから児童生徒を守り通す義務があります。教員含め学校側は、それをしっかりと意識し、いじめ防止対策推進法および国の基本方針について理解しておく必要があります。
また、いじめで苦しんでいる子どもたちは、本法律によって学校や国から守られる権利があることが示されています。各学校には、いじめから児童生徒を守り通すための組織の設置が義務付けられており、相談を受けていじめを認知した場合は、学校が一丸となって対処をするよう定められています。
また、教育委員会や警察など、いじめを許さない立場の大人は多くいます。いじめ防止対策推進法でも、以下のように定められています。
国・地方公共団体・学校の設置者や教職員の責務
(国の責務)
第五条 国は、第三条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(学校の設置者の責務)
第七条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。
(学校及び学校の教職員の責務)
第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
いじめの防止・対策は、国の責務です。ひいては、この国に住む私たち大人全員の責務と言っても過言ではありません。
本法で定められた学校の施策、および組織的対応により、一人でも多くの子どもがいじめから適切に守られることを願います。
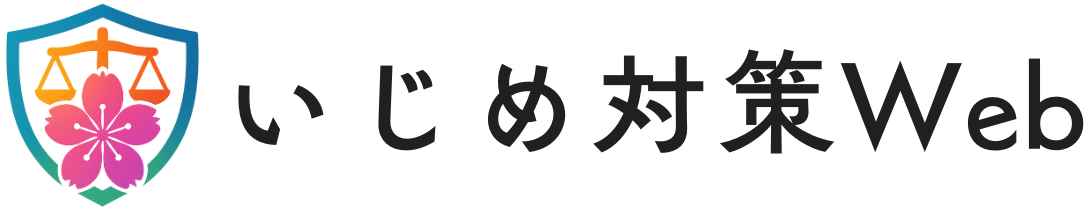







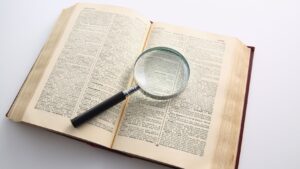
コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 2013年(平成25年)成立のいじめ防止対策推進法の第22条により、各学校には「いじめの防止等の対策のための組織」を置くことが義務付けられています。 […]
[…] 本記事ではいじめ防止対策推進法の第22条に定められている、いじめの防止等の対策のための組織(学校いじめ対策組織)が形骸化・機能停止していた事例についてまとめます。 […]