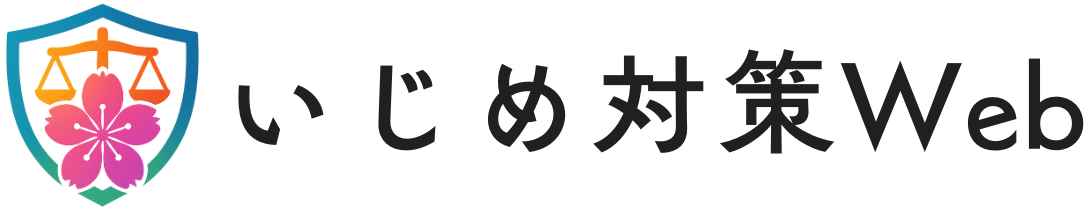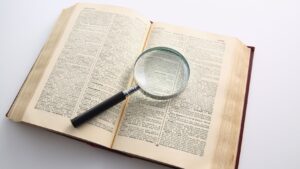集団規範はいじめを防止する|大西彩子氏「いじめ加害者の心理学」

昔から学校や社会全体でいじめの防止に取り組んでいますが、なかなか根絶には至りません。
いじめを効果的に防ぐには、いじめの加害者側の心理や、それが生まれる学校や学級の構造を深く理解することも一つの手です。
今回は、いじめ研究の第一人者である大西彩子氏の論文および書籍(「いじめ加害者の心理学―学級でいじめが起こるメカニズムの研究」)の内容をもとに、いじめ防止における集団規範の重要性と行うべき取り組みについて考察します。
集団規範はいじめを防止する
大西彩子氏の書籍「いじめ加害者の心理学―学級でいじめが起こるメカニズムの研究」の目的は、集団規範によるいじめ防止モデルを提案することと述べられています。
まずは集団規範とは何なのかについて、まとめていきます。
集団規範とは
いじめ防止に関わる集団規範とは何かについて、大西氏は、1963年の佐々木薫氏による論文(「集団規範の研究概念の展開と方法論的吟味」)をもとに以下のような定義を採用しています。
集団規範は「集団成員の相互作用が進むとその所産として形成されるもので、繰り返し生起する一範疇の事態において、集団の全メンバーに共通に妥当すると認知されている特定の行動型に同調するよう、集団メンバーに作用する社会的合う力の合成されたもの」(佐々木,1963)と定義される。
(大西彩子,2015「いじめ加害者の心理学:学級でいじめが起こるメカニズムの研究」p.12より)
この集団規範ですが、簡単に言えば、「集団の雰囲気」みたいなものと捉えて良いと思います。
つまりはクラスや学校において、いじめはよくないという雰囲気があるか、それともいじめを容認するような雰囲気があるか、ということが重要になってくるというわけです。
集団規範がいじめ加害傾向に影響する
本研究によって、いじめに否定的な集団規範が高い学級では、生徒のいじめ加害傾向が低いことが示された。
(大西彩子,2015「いじめ加害者の心理学:学級でいじめが起こるメカニズムの研究」p.80より)
中学校14学級を対象に質問紙調査を実施した結果により、集団規範がいじめ加害傾向に影響することが明らかになったとのことです。
よって、学級内にて個々の生徒がいじめに対して否定的であり、その雰囲気が作られていることが、いじめ防止には重要であるといえるわけですね。
いじめに否定的な集団規範を高めるには教師の態度が重要
いじめに否定的な集団規範を改善するためのアプローチについて、大西氏は「いじめ加害者の心理学―学級でいじめが起こるメカニズムの研究」の書籍内にて様々な視点から言及しています。
その中の一つに、「教師の態度」が挙げられています。
教師が日常的に児童・生徒に対して受容的で親近感があり、自信をもった客観的な態度を示すことが、いじめに否定的な学級規範を高める効果をもつことが明らかになった。
(大西彩子,2015「いじめ加害者の心理学:学級でいじめが起こるメカニズムの研究」p.80より)
教師がしっかりとした態度で児童生徒に接していることが、いじめが起こりにくい学級の雰囲気づくりには重要であるということですね。

受容・親近・自信・客観に関する教師認知が重要とのことです。
いじめに否定的な集団規範を高める取り組みの考察
大西彩子氏の研究により、いじめに否定的な集団規範を高めることが、いじめ防止に重要であると明らかになりました。
また、大西氏は集団規範によっていじめを防止する利点について、児童・生徒がいじめを制止する可能性が高くなることや、より多くの目によっていじめの有無を監督できることを挙げています。
いじめに教師がなかなか気づけない時でも、周りの生徒がサポートできる環境であれば、いじめに苦しむ子どもを救える可能性が高まります。
学校におけるいじめの予防対策を考えていくにあたり、集団規範を高めるための取り組みを導入していくことはマストといえるでしょう。
学校いじめ対策組織による集団規範を高める取り組み
私が提案したいのは、学校いじめ対策組織による学校全体の集団規範を高める取り組みです。
学校いじめ対策組織は、国の基本方針により、児童生徒及び保護者に対して,自らの存在及び活動が容易に認識される取組を実施する必要があると述べられています。
学校いじめ対策組織が積極的に存在をアピールし、いじめを絶対に許さないという姿勢や取り組みを示すことで、児童生徒内におけるいじめに否定的な集団規範を高めることができると考えています。


一人ひとりの教職員がいじめに対して意識を高く持ち、生徒から信頼されることはもちろん重要なことです。
しかし、すべての教員が善人とは限りませんし、多忙化によっていじめ対策に集中できないこともあるかと思われます。
そのため、いじめ対策には組織的対応が肝心です。予防の段階から、学校いじめ対策組織による組織的な取り組みを進め、いじめを許さない学校規範を作っていくことが、いじめゼロに向けて重要なことであると私は考えています。
現状では、学校いじめ対策組織の形骸化によるいじめ重大事態の発生も多く報告されています。
生徒指導提要においても、「いじめへの対応において、組織が効果的に機能していないために重大事態が引き起こされるケースが見られることから、学校内外の連携に基づくより実効的な組織体制を構築することが課題となっています。」(p.125)との記載が見られます。


学校に求められる組織的対応について、多くの人が正しい知識を得るとともに、今後は学校いじめ対策組織や組織的対応に関する研究が積極的に進むことを期待しています。