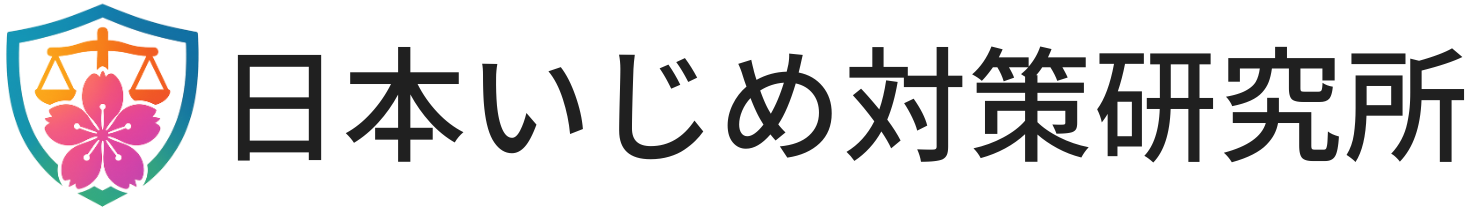いじめの防止等の対策のための組織(以下、学校いじめ対策組織)が形骸化していた事例や、そもそも不設置であったり教員の誰も認識していなかった事例についてまとめます。
本記事で扱う事例にあたっては、今までインターネット上で公表されてきたいじめ重大事態調査報告書より、学校いじめ対策組織や学校いじめ防止基本方針が形骸化していたと指摘されている部分を引用します。
前回の内容に当たる記事については以下のリンクからご覧ください。

令和5年 太子町の町立学校におけるいじめ重大事態
令和5年度に太子町立学校にて発生したいじめ事案に関する調査報告書が、令和7年9月 26 日に太子町教育委員会より公表されました。
本調査報告書からは、以下の文章の記載が認められました。
「校長は法で定められたいじめ対策組織を設置せず、重大事態の可能性がある状況でも体制を構築しなかった。」
「令和5年度に太子町立学校にて発生したいじめ事案に関する調査報告書(公表版)」p.2 (2025, 太子町教育委員会)
学校いじめ対策組織の設置は、いじめ防止対策推進法の第二十二条に定められた学校の義務です。
組織の不設置は法令違反のように思われますが、学校に対してどのような責任問題になったのかの記述は見受けられませんでした。
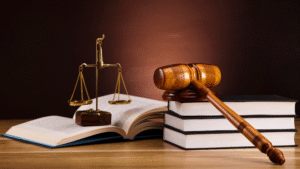
組織的対応の欠如がいじめを深刻化させた
今回の調査報告書は、そもそも学校いじめ対策組織が設置されていないという衝撃的な内容です。
本事例について、その他の関連する記載は以下の通りです。
「Aの状況を把握した学校は簡易な聞き取りをおこない、個別の注意 ・見守りにとどまり、いじめの認定やいじめ対策組織による対応、保護者への十分な説明は行われなかった。」
「令和5年度に太子町立学校にて発生したいじめ事案に関する調査報告書(公表版)」(2025, 太子町教育委員会)
このような組織的対応の欠如が、いじめの事態を深刻化させたとの見方が報告書内でもされています。
令和5年 網走市の中学校におけるいじめ重大事態
網走市の中学校における生徒が令和2年から令和3年にかけて重大事態に該当し得るいじめを受けた事案について、網走市いじめ問題調査委員会からの調査報告書が令和6年12月18日に公表されました。
調査報告書からは、以下の文章の記述が認められました。
「教員らへの聴取の結果、T1校長やT2教頭を含め、『生徒指導会議』なる組織を認識している教員は一人もいなかった。また、『生徒指導会議』という名称ではないにしても、いじめ防止対策組織について尋ねると、本件をはじめとする3件の事案について重大事態として調査することを契機に初めて設置されたとの認識を持っている教員がほとんどであった。さらに、学校の資料や教員らの発言からは、各重大事態には至らないもののいじめに該当する事実は、本件の発覚以前も複数発生していたと考えられるが、そのいずれにおいてもいじめ防止対策組織は機能していなかったと考えられる。このように、学校においては、いじめ防止対策組織が設置されていたとはいえない状況であったと言える。なお、多くの教員において、いじめ防止対策組織は、個別の事案に対して臨時で設置されるとの認識であったが、上記法の規定と解釈からすれば、この認識は誤りである。」
「いじめの重大事態に係る調査報告書」(2024, 網走市いじめ問題調査委員会)
本校の学校いじめ対策組織は、「生徒指導会議」という名称であったようですが、校長などの管理職を含めて誰も認知していなかったという調査報告が出ています。
学校いじめ対策組織がいじめ発覚後に設置されるという誤認
本件において、「いじめ防止対策組織はいじめが発覚してからや重大調査が始まってから設置される」という認識を持っている教員が多かったというのも、ありがちな間違った認識であるように思われます。
学校いじめ対策組織は常設され、日ごろからいじめの防止対策に努める必要があり、さらに児童生徒から信頼される相談の窓口であると認識される必要があります。

本事案は、現代の学校現場における問題点を如実に表しているかもしれません。
令和5年 相生市の中学校におけるいじめ重大事態
令和5年3月11日、兵庫県相生市にて中学生が自死した事案について、相生市児童等に関する重大事態調査委員会より、2024(令和6)年4月16日に調査報告書が公表されました。
調査報告書からは、以下の文章の記述が認められました。
「当該校では,そもそもいじめ防止組織が稼働したことはない。」
「調査報告書」p.86 (2024, 相生市児童等に関する重大事態調査委員会)
本事案も、学校いじめ対策組織が何も本来の役割を全うできず、明らかに形骸化しています。
学校いじめ対策組織が生徒指導委員会等と兼ねている弊害
今回の重大事態調査報告書における、関連する記載は以下の通りです。
「当時の校長は,生活指導委員会が、いじめ対応チームを兼ねていると考えていたようであるが,当該校の基本方針は,このような考え方には立脚していないし,当時の校長以外の教員らは,このような考えではなく,いじめ対応チームが立ち上がったことはないという認識であった。」
「調査報告書」 (2024, 相生市児童等に関する重大事態調査委員会)
「当該校の教員らは,当時の校長も含めて,いじめ対応チームの機能を理解していなかったのである。」
「調査報告書」 (2024, 相生市児童等に関する重大事態調査委員会)
学校いじめ対策組織が、他の生徒指導に関わる委員会などと兼ねているケースはよく見られます。
しかし、それが組織への軽視、ならびに実質的に機能停止に繋がっていると考えるべきでしょう。