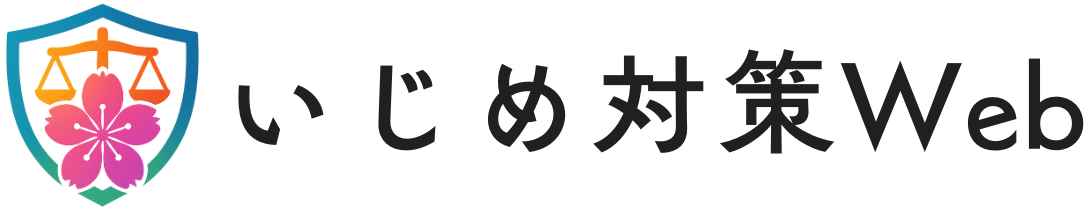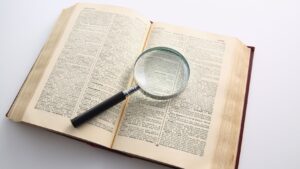いじめは教育で解決できるか?「いじめゼロ!ある公立中学校が実現したいじめ撲滅」レビュー

学校現場で起きるいじめは、子どもの心身に大きな傷を残し、時には取り返しのつかない結果を招くこともあります。
これまで様々ないじめ対策のための対応策が考えられ、学校教育でもいじめ防止のための授業が行われてきました。
確かに教育がうまく機能すれば、いじめが発生しにくい風土をつくることは可能だと思われます。
しかし、いじめには家庭環境や社会的な背景、インターネットを介した匿名性など、教育の枠を超える要因も絡んでいることがあり、教師がいくら努力しても、子どもたちが学校外で受ける影響をコントロールすることは難しいでしょう。
果たして、いじめは教育によって解決できるのでしょうか。
今回は、中嶋博行氏による「いじめゼロ!ある公立中学校が実現したいじめ撲滅」という本の内容を基に、考察していきたいと思います。
いじめ問題は人間教育で解決できるのか
いじめ問題の解決にあたり、教育だけでなんとかしようという方針は果たして正しいのでしょうか。
いじめは教育解決できるという風潮
中嶋博行氏は「いじめゼロ!ある公立中学校が実現したいじめ撲滅」の著書の中で、以下のように述べています。
多くの人々は「人間教育でいじめ問題を解決できる」という信念をもっています(人間教育至上主義)。
(中嶋博行, 2009,「いじめゼロ!ある公立中学校が実現したいじめ撲滅」p.62より)
確かに、学校現場ではいじめなどの問題を、教育で解決しようとする風潮があると見受けられます。
学校が警察の介入を嫌うというのも、よく指摘されている話です。
いじめ対策に当たり、道徳でいじめがいけないことだと学んだり、いじめ予防のための教育プログラムの開発や効果検証も行われているものの、それが果たしていじめ加害者の減少に本当に繋がっているかは何とも言えない部分です。
事実として、日本ではいじめ認知件数も重大事態の件数も年々増加しています。

鬼畜の心に教育は無力であるという意見
人間教育の大切さを訴える意見に対し、中嶋氏は、こうした考え方がいじめを放置することになるとの旨を述べています。
人間教育が成り立つには、生徒たち自身、「人間の心」をもっていることが必要です。動物園のオランウータンやゴリラに道徳を説いてもチンプンカンプンなように、「鬼畜の心」に人間教育をほどこしてもおそらく無駄でしょう。
(中嶋博行, 2009,「いじめゼロ!ある公立中学校が実現したいじめ撲滅」p.63-64より)
本著では、実際に学校現場で行われた凄惨ないじめ事件の数々を最初に紹介しています。
集団による暴行、果ては自殺に追い込むまでエスカレートしたいじめに対し、そのような行為をする鬼畜な心に、教育は無力ではないのかという意見は確かに尤もであると聞こえます。
教育に即効性はない
もともと教育に即効性はありません。
(中嶋博行, 2009,「いじめゼロ!ある公立中学校が実現したいじめ撲滅」p.64より)
いじめ加害者が必ずしも、教育によって改心しないとは限りません。しかし、それには長期間に渡る教育が必要になることもあります。
形だけの「謝罪会」が、いじめの放置・深刻化に繋がっているとの指摘もあります。
いじめられた生徒をすぐに助けるために、教育ではなく、警察のような力の介入が必要な場面もあるはずです。
いじめは犯罪問題である
本書の主張の一つに、いじめを教育問題ではなく犯罪問題として捉えることが肝要であるというものがあります。
いじめ加害者に償いをさせる
いじめの加害者にどう対処するかというのは、現代における大きな課題です。
中嶋氏は、本書の目的について、以下のように述べています。
この本の目的は学校からいじめを根絶して、いじめの加害者に償いをさせることです。
(中嶋博行, 2009,「いじめゼロ!ある公立中学校が実現したいじめ撲滅」p.15より)
現在の教育現場は、いじめをする生徒の立ち直りを重視していると中嶋氏は言及しています。
確かに、いまの教育現場では体感的に、加害者の更生が重視される風潮があります。
しかし、筆者も言うように、最も重要視すべきは被害者の救済であるべきです。
いじめ被害者が学校を追われるのはおかしい
いじめ被害者は罪がないにも関わらず学校を去り、いじめ加害者が学校に居座るというのは、今の学校現場のよくある現状です。
不登校の増加は現代の大きな教育問題であり、重大事態調査報告書を見てみても、いじめによる不登校の数は少なくありません。
「いじめ宿命論」が被害者救済を阻み、いじめを助長する
(中嶋博行, 2009,「いじめゼロ!ある公立中学校が実現したいじめ撲滅」p.74より)
いじめ宿命論とは、簡潔に言えば、「いじめられる側にも問題がある」というような考え方や論のことだと私は解釈しました。
いじめ宿命論の代表的な説として、いじめられやすいタイプの生徒は無理に学校にこだわらず、学校の外に自分の世界を求めればいいというような論理です。
これは、一見正しいような優しいような主張に見えますが、しかし加害者が学校に居座り被害者が学校を追われる現状を肯定してしまっている意見であると著者は批判しています。私もその通りだと思います。
いじめ被害生徒は絶対に悪くない
いじめられた側にも責任はあるのか、という問題に対し、中嶋氏はいじめ被害生徒は絶対に悪くないという意見に賛同しています。
私もこの問題については全くの同意見です。以下の記事でも述べていますが、いじめは、いじめた側が100%悪いのであり、いじめられた側の生徒の責任や原因については議論すること自体がナンセンスです。

また、中嶋氏は、いじめに責任があるのはクラス全体ではなく、あくまで実行犯の加害生徒であると主張しています。
そのうえで、加害生徒に厳格な償いをさせることを主張しています。
加害生徒に出席停止を命じないで、被害者のほうに「学校を休みなさい」というのは本末転倒、いかにも不甲斐ない話です。
(中嶋博行, 2009,「いじめゼロ!ある公立中学校が実現したいじめ撲滅」p.95より)
学校からいじめをなくすために
やはりいじめ対策を考えるにあたって重要なのは、学校からいじめをなくすためにはどうすればいいのかという点です。
中嶋氏は、アメリカの教育現場での「ゼロ・トレランス(不寛容)方式」や「スクールポリス」を例に挙げ、犯罪抑止の切り札は「力の論理」にあると主張しています。
そのうえで、学校からいじめをなくすために、以下のような三つの提案をしています。
1.学校にいじめ情報収集部と校内パトロール部隊をつくり、学校ぐるみの監視体制を実現する。
2.いじめを発見したら中心的な加害生徒をピンポイントで処分する。
3.学校と警察の情報提供制度、警察官のいじめ調査権限などの新制度を利用して、暴力的ないじめは即刻、警察に通報する。
(中嶋博行, 2009,「いじめゼロ!ある公立中学校が実現したいじめ撲滅」p.183より)
これらの提案に対し、加害生徒への人権配慮や教育的配慮も大事だという意見も出そうですが、しかし中途半端な姿勢が被害生徒を苦しめることになると中嶋氏は主張します。
私も、いじめに対しては徹底的に許さない姿勢を持つことが、今の学校には求められていると思います。
この提案の中で、特にいじめ情報収集部と校内パトロール部隊をつくるというのは、いじめ加害者に対する抑止力として非常に有効だと思います。
また、本来その役割を担うのは、いじめ防止対策推進法22条に規定されている、学校いじめ対策組織であると私は考えています。

本書はもともと2006年に朝日新聞社より刊行された『君を守りたい いじめゼロを実現した公立中学校の秘密』を改題したものであるそうです。
2013年のいじめ防止対策推進法以降は、学校の組織的対応が重視されています。校内パトロール部隊というのも、外国のいじめ対策プログラムであるKiVaなどでも取り入れられている仕組みです。
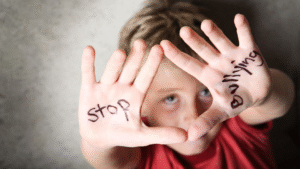
本書の提言を基に、いま一度、学校いじめ対策組織に求められる役割を再考してみるべきではないでしょうか。
いじめに対して教育を実施することは確かに重要です。しかし、それだけでは不十分であることと、いじめを教育問題として捉えることが時に被害者を苦しめている事実から目を背けてはなりません。
私は、学校に関わる人々がいじめ対策について深い知見と強い意思を持ち、学校におけるいじめ対策組織が警察に負けないくらいの抑止力を持つことができれば、必ずいじめは減らせると信じています。